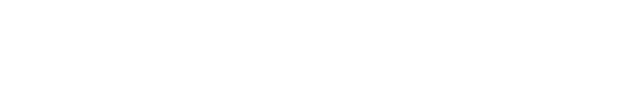奈良・王寺でピロリ菌の検査と治療
「胃の不調が続く」「胃がんのリスクが心配」と感じていませんか? もしかしたら、それはピロリ菌が原因かもしれません。ピロリ菌は胃の中に住み着き、様々な病気を引き起こす細菌です。奈良県王寺にお住まいの方で、ピロリ菌の感染が気になる方、適切な検査と治療を受けたい方は、ぜひ南王寺診療所にご相談ください。
ピロリ菌とはどんな病気?
ピロリ菌、正式名称を「ヘリコバクター・ピロリ」といい、ヒトの胃の中に生息するらせん形をした細菌です。胃の中は強い酸性のため、通常の細菌は生きていくことができません。しかし、ピロリ菌はウレアーゼという酵素を生成し、尿素をアンモニアと二酸化炭素に分解することで、胃酸を中和し、自らが生息できる環境を作り出します。
ピロリ菌は、一度感染すると自然に除菌されることはほとんどなく、長期間にわたって胃の中に住み着き続けます。この持続的な感染が、胃の粘膜に炎症を引き起こし、様々な胃の病気の原因となります。特に、慢性胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍といった消化器疾患との関連が深く、さらには胃がんの発生リスクを高めることも明らかになっています。そのため、胃の不健康を感じている方や、胃がんのリスクを減らしたいと考えている方にとって、ピロリ菌の検査と適切な治療は非常に重要です。
ピロリ菌の主な症状
ピロリ菌に感染しても、必ずしも自覚症状が現れるわけではありません。しかし、長期間にわたって感染が続くと、胃の粘膜に炎症が起き、様々な症状が現れることがあります。これらの症状は、日常生活に支障をきたすだけでなく、病気の進行を示唆する場合もあります。
ピロリ菌感染による代表的な症状としては、胃の痛みや不快感が挙げられます。特に食後に胃がもたれる、張るといった症状や、みぞおちのあたりがキリキリと痛むといった症状が見られることがあります。また、吐き気や嘔吐、食欲不振といった消化器症状も現れることがあります。さらに、原因不明の貧血が続く場合も、ピロリ菌による慢性的な胃からの出血が原因となっている可能性も考えられます。これらの症状は、他の胃の病気でも見られることがあるため、自己判断せずに専門の医療機関を受診し、適切な検査を受けることが重要です。
ピロリ菌の原因
ピロリ菌の感染経路は、主に経口感染であると考えられています。特に幼少期の衛生環境が十分に整っていない時代や地域において感染しやすい傾向があります。かつての日本では、井戸水や乳幼児期の食物などからの感染が多かったとされていますが、現代では衛生環境の改善により新規感染者は減少しています。
具体的な感染経路としては、ピロリ菌に感染している家族からの感染が挙げられます。例えば、感染者の便中に含まれるピロリ菌が、手などを介して口に入ってしまう「糞口感染」や、感染者の唾液を介して感染する「経口感染」が考えられます。また、乳幼児期に離乳食などを介して親から子へ感染するケースも報告されています。そのため、ご家族にピロリ菌感染者がいる場合や、過去にそのような環境で育った方は、ご自身も感染している可能性を考慮し、検査を検討することをおすすめします。
ピロリ菌の治療
ピロリ菌の治療は、主に「除菌療法」と呼ばれる薬物療法によって行われます。この治療法は、複数の薬剤を同時に服用することで、胃の中に生息するピロリ菌を効果的に死滅させることを目的としています。除菌療法は、胃の病気の改善だけでなく、将来的な胃がんのリスク低減にもつながるため、ピロリ菌感染が確認された場合には積極的に推奨されます。
具体的な除菌療法としては、一般的に「プロトンポンプ阻害薬」という胃酸の分泌を抑える薬と、2種類の「抗菌薬」を組み合わせた3剤併用療法が主流です。これらの薬を1日2回、7日間服用します。治療中は、指示された通りに薬を服用することが非常に重要です。もし途中で服用を中止したり、飲み忘れたりすると、除菌が不成功に終わる可能性があります。治療後には、除菌が成功したかどうかを確認するための検査を行います。万が一、初回で除菌が不成功だった場合でも、薬の種類を変更して再度除菌療法を行うことが可能です。南王寺診療所では、患者様の状態に合わせた適切な除菌療法を提案し、安心して治療を受けていただけるようサポートいたします。ご自身の胃の健康のためにも、ぜひ一度ご相談ください。