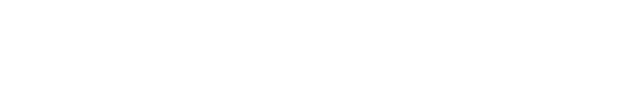奈良・王寺で食道がんの検査と治療
食道がんは、自覚症状が出にくいがんです。
早期発見・早期治療が非常に重要ですが、どのような症状に注意し、どのような検査や治療があるのかご存知でしょうか。
このページでは奈良県王寺町の南王寺診療所が、食道がんの基本的な知識から、主な症状、原因、そして治療法について詳しく解説します。
食道がんとはどんな病気?
食道がんは、食道の粘膜から発生する悪性の腫瘍です。
食べ物や飲み物が口から胃へと運ばれる通り道である食道にできるため、進行すると飲食が困難になるなど、生活の質に大きな影響を及ぼします。
早期の段階では自覚症状がほとんどないため、気づきにくいのが特徴です。
しかし、がんが進行するにつれて、様々な症状が現れるようになります。
食道がんの多くは食道の粘膜の表面に発生し、徐々に深部に浸潤していきます。
食道がんには、その組織型によっていくつかの種類がありますが、日本人では扁平上皮がんが約90%を占めています。
扁平上皮がんは、食道の上皮細胞から発生するがんで、飲酒や喫煙との関連が深いとされています。
その他、腺がんや未分化がんなどがありますが、これらは比較的稀です。
食道がんの発生部位は、食道のどの部分にも起こりえますが、特に中部や下部に多く見られます。
食道がんの進行度は、がんの大きさ、深さ、リンパ節転移の有無、遠隔転移の有無などによってステージ分類され、これに基づいて治療方針が決定されます。
食道がんの早期発見には、定期的な健康診断や内視鏡検査が非常に有効です。
特に、喫煙や飲酒の習慣がある方、あるいは家族に食道がんの既往がある方は、積極的に検査を受けることをお勧めします。
早期に発見できれば、内視鏡的切除など体への負担が少ない治療法で完治が期待できるケースも少なくありません。
そのため、食道がんに関する正しい知識を持ち、疑わしい症状があればすぐに医療機関を受診することが大切です。
食道がんの主な症状
食道がんが進行すると現れる具体的な症状について解説します。
食道がんの初期段階では、自覚症状がほとんど現れないため、発見が遅れることがあります。
しかし、がんが進行し、食道の内部を狭めたり、周囲の臓器に影響を及ぼすようになると、様々な症状が現れるようになります。
これらの症状は、他の病気でも見られることがあるため、食道がん特有のものではないこともありますが、見過ごさずに医療機関を受診することが重要です。
最も特徴的な症状の一つに「食べ物がつかえる感じ」があります。
これは、食道の内部ががんによって狭くなることで、固形物だけでなく、時には水分でもつかえたり、飲み込みにくくなったりする感覚です。
最初は特定の食べ物で感じる程度でも、進行すると柔らかいものや液体でも症状が現れることがあります。
また、「胸の違和感や痛み」も食道がんの症状として現れることがあります。
これは、食道が胸の内部に位置するため、がんによる炎症や浸潤が原因で起こる可能性があります。
初期の段階では漠然とした不快感ですが、進行すると持続的な痛みとなることもあります。
その他、「声のかすれ(嗄声)」も食道がんの症状の一つです。
これは、がんが進行し、声帯を動かす神経(反回神経)を圧迫することで生じます。声帯麻痺によって声がかすれるため、風邪でもないのに声がかすれる状態が続く場合は注意が必要です。
また、原因不明の「体重減少」や「咳、血痰」なども食道がんの進行を示唆する症状として挙げられます。
食道がんが原因で栄養摂取が困難になったり、食道からの出血があったりすると体重減少や血痰が見られることがあります。
これらの症状が複数現れている場合は、すぐに専門医の診察を受けるべきです。
食道がんの原因
食道がんの発生リスクを高める主な要因について説明します。
食道がんの発生には、様々な要因が複雑に絡み合っていますが、特に生活習慣と関連が深いとされています。
食道がんの多くを占める扁平上皮がんの場合、特定の生活習慣がリスクを大幅に高めることがわかっています。これらのリスク因子を理解し、可能な範囲で避けることが、食道がんの予防につながります。
最も主要なリスク因子として挙げられるのが「喫煙」です。タバコの煙に含まれる発がん性物質が食道の粘膜に直接作用することで、がんのリスクを高めます。喫煙期間が長く、喫煙量が多いほど、食道がんの発生リスクは顕著に上昇します。また、喫煙と「飲酒」が同時に行われることで、そのリスクは相乗的に高まると言われています。アルコールは食道粘膜に炎症を引き起こし、発がん性物質の作用を助長すると考えられています。特に、熱い飲み物や刺激の強いアルコールを習慣的に摂取する方は注意が必要です。
その他、「熱い飲食物の摂取」も食道がんのリスクを高める要因とされています。高温の飲食物が食道粘膜を繰り返し刺激することで、細胞のDNAに損傷を与え、がん化を促進する可能性があると考えられています。また、「食道炎」や「バレット食道」などの食道に慢性的な炎症を引き起こす病気も、食道がんのリスクを高めます。バレット食道は、胃酸の逆流によって食道の粘膜が変化する病気で、腺がんのリスクを上昇させることが知られています。
さらに、野菜や果物の摂取不足、過度の飲酒、肥満なども食道がんのリスク因子として挙げられています。また、特定の遺伝的要因も食道がんの発生に関与している可能性が指摘されています。これらのリスク因子に心当たりのある方は、定期的な健康チェックや生活習慣の見直しを検討することをお勧めします。早期にリスクを認識し、適切な対策を講じることが、食道がんの予防に繋がります。
食道がんの治療
食道がんの治療法は、がんの進行度や患者様の状態によって多岐にわたります。 食道がんの治療は、がんの進行度(ステージ)、患者様の全身状態、年齢、合併症の有無などを総合的に判断して決定されます。早期に発見された場合と進行している場合とでは、選択される治療法が大きく異なります。治療の選択肢は多岐にわたりますが、主なものとしては、内視鏡治療、手術、放射線治療、化学療法(抗がん剤治療)などがあります。これらの治療法は単独で行われることもあれば、組み合わせて行われることもあります。
早期の食道がんであれば、「内視鏡治療」が選択されることがあります。これは、口から内視鏡を挿入し、がんのある粘膜を切除する方法です。体への負担が少なく、回復も早いというメリットがあります。代表的な内視鏡治療には、内視鏡的粘膜切除術(EMR)や内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)があります。これらは、がんが粘膜の表面にとどまっていて、リンパ節転移の可能性が低い場合に適用されます。
がんが進行し、内視鏡治療が難しい場合には、「手術(食道切除術)」が主な治療選択肢となります。手術では、がんのある食道の一部または全部を切除し、残った食道と胃や大腸の一部などをつなぎ合わせます。手術は体への負担が大きい治療ですが、根治を目指せる可能性のある治療法です。近年では、体に負担の少ない胸腔鏡手術やロボット支援下手術も導入されています。手術後は、食事の摂り方や生活習慣に注意が必要となります。
また、「放射線治療」や「化学療法(抗がん剤治療)」も食道がんの重要な治療法です。放射線治療は、高エネルギーの放射線をがん細胞に照射して、がんを死滅させる治療です。手術が困難な場合や、手術後の再発予防、あるいは手術前にがんを縮小させる目的で行われることがあります。化学療法は、抗がん剤を点滴や内服で投与し、全身のがん細胞に作用させる治療です。手術の前後に補助的に行われることもあれば、進行がんに対して単独で、あるいは放射線治療と併用して行われることもあります。これらの治療法は、患者様一人ひとりの状態に合わせて最適な組み合わせが検討されます。